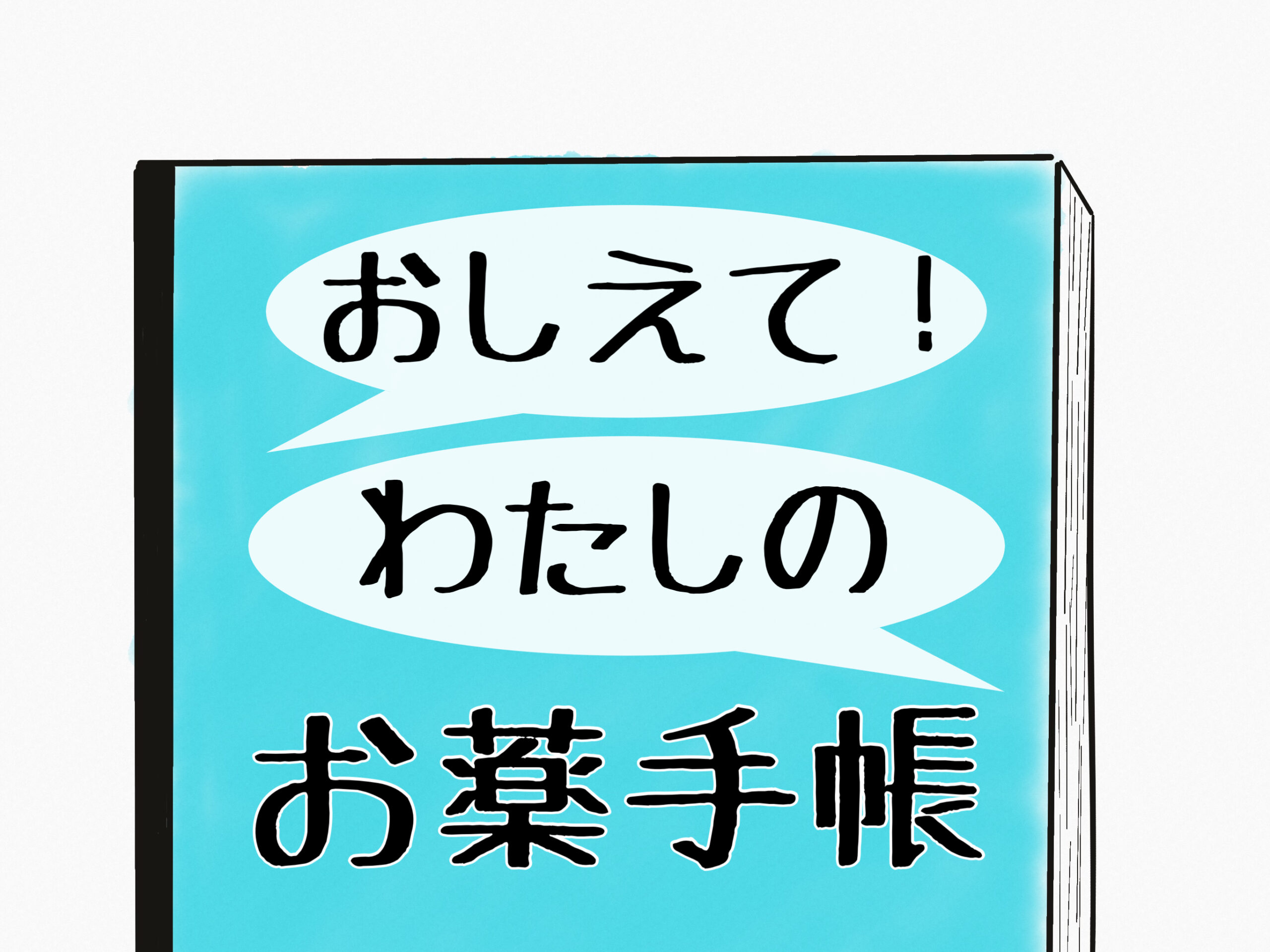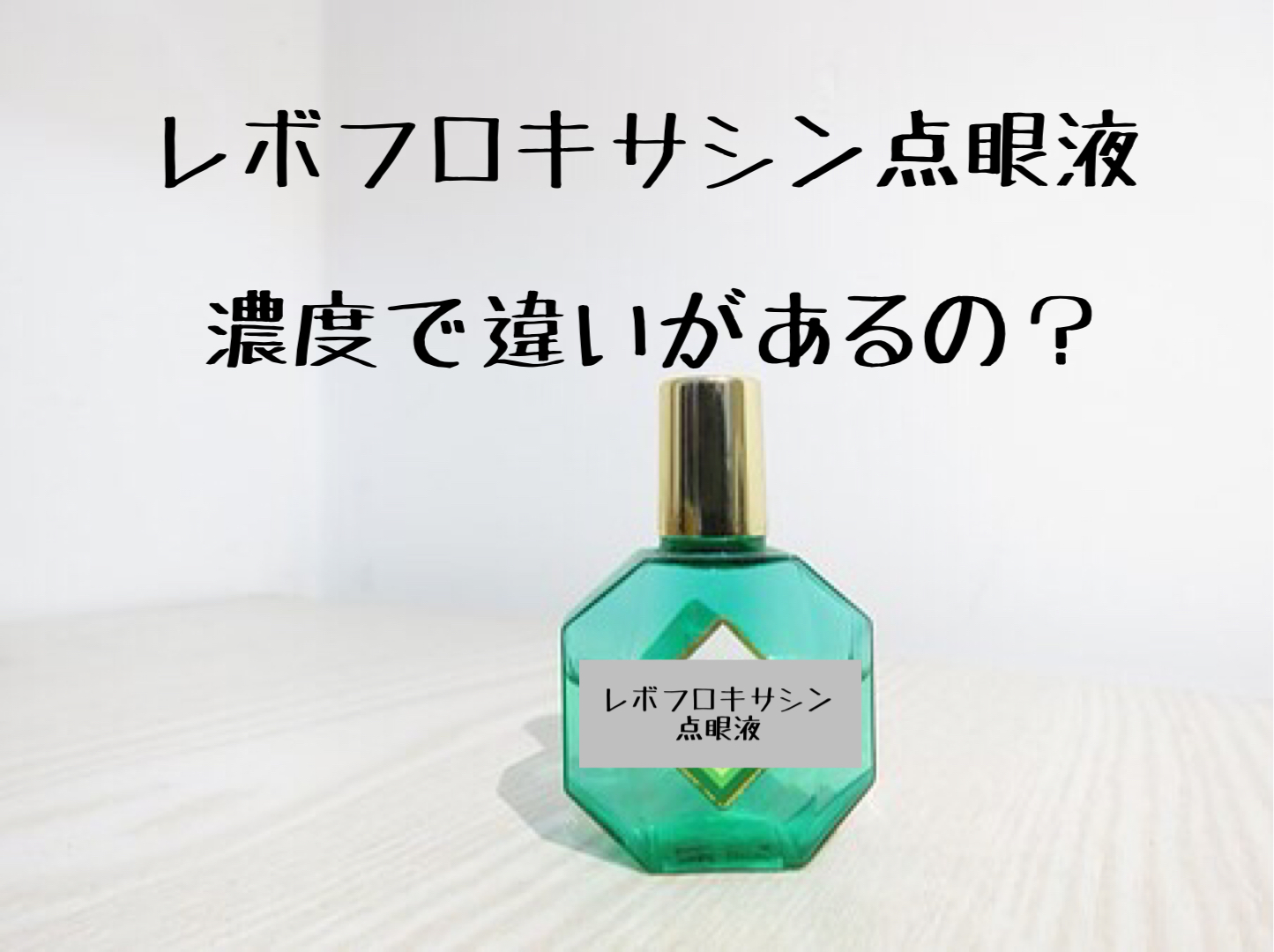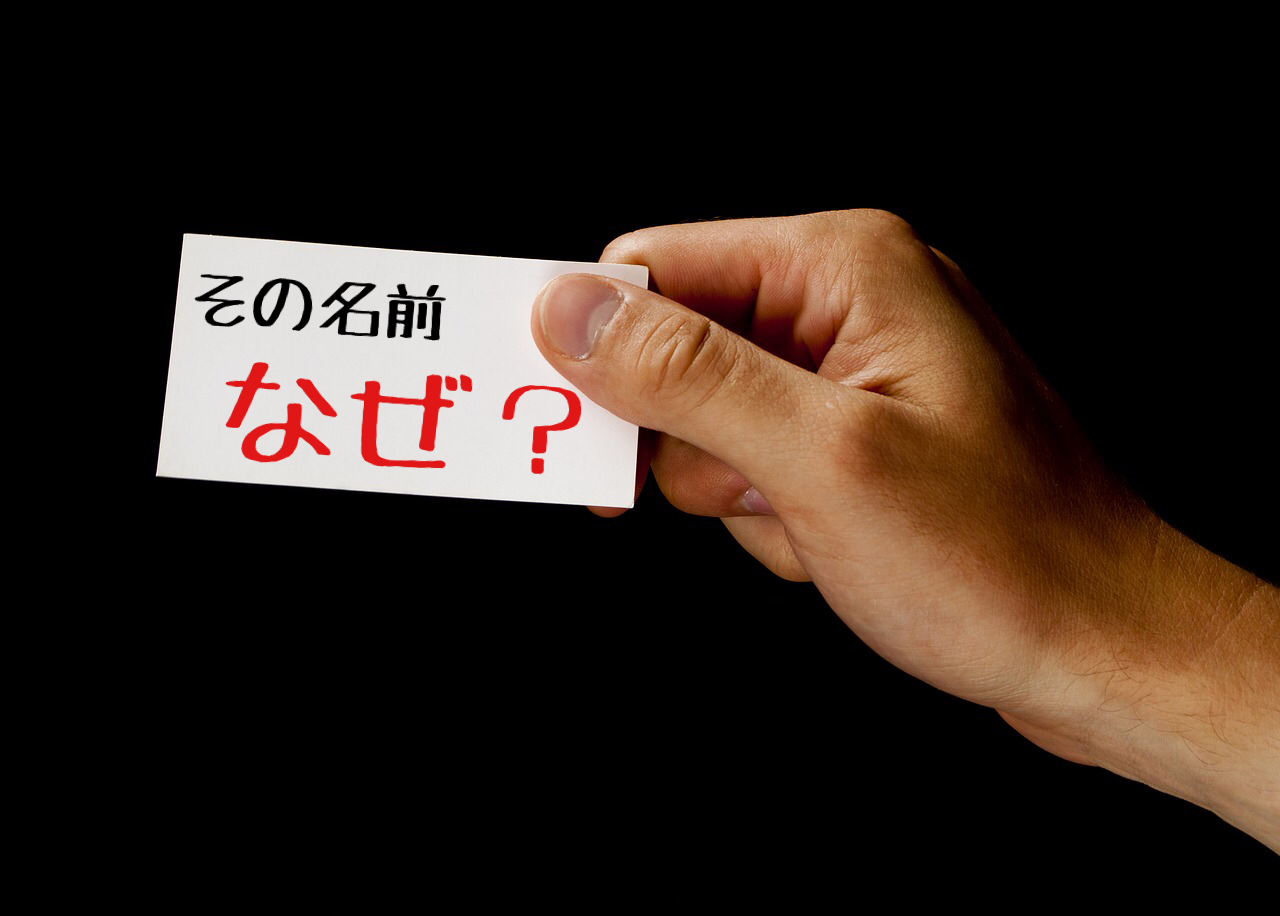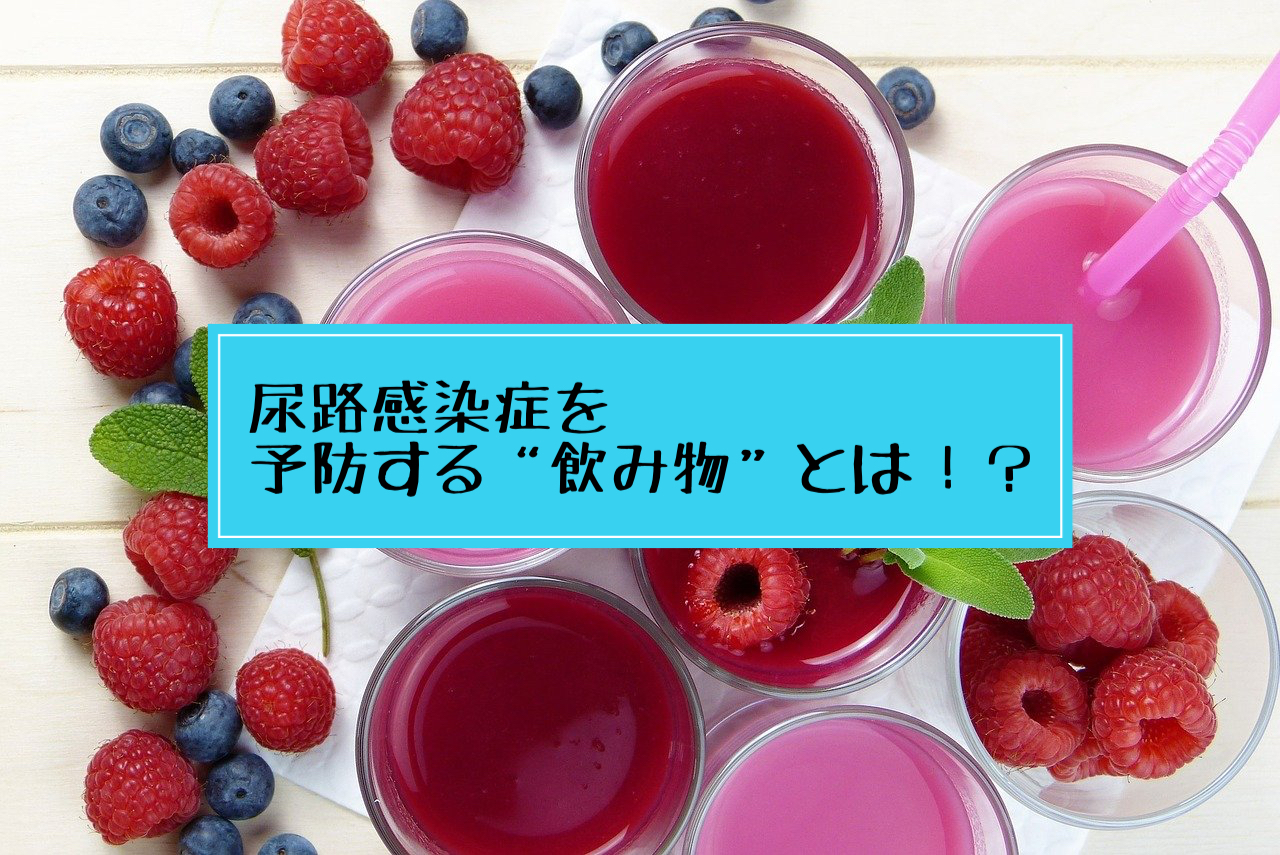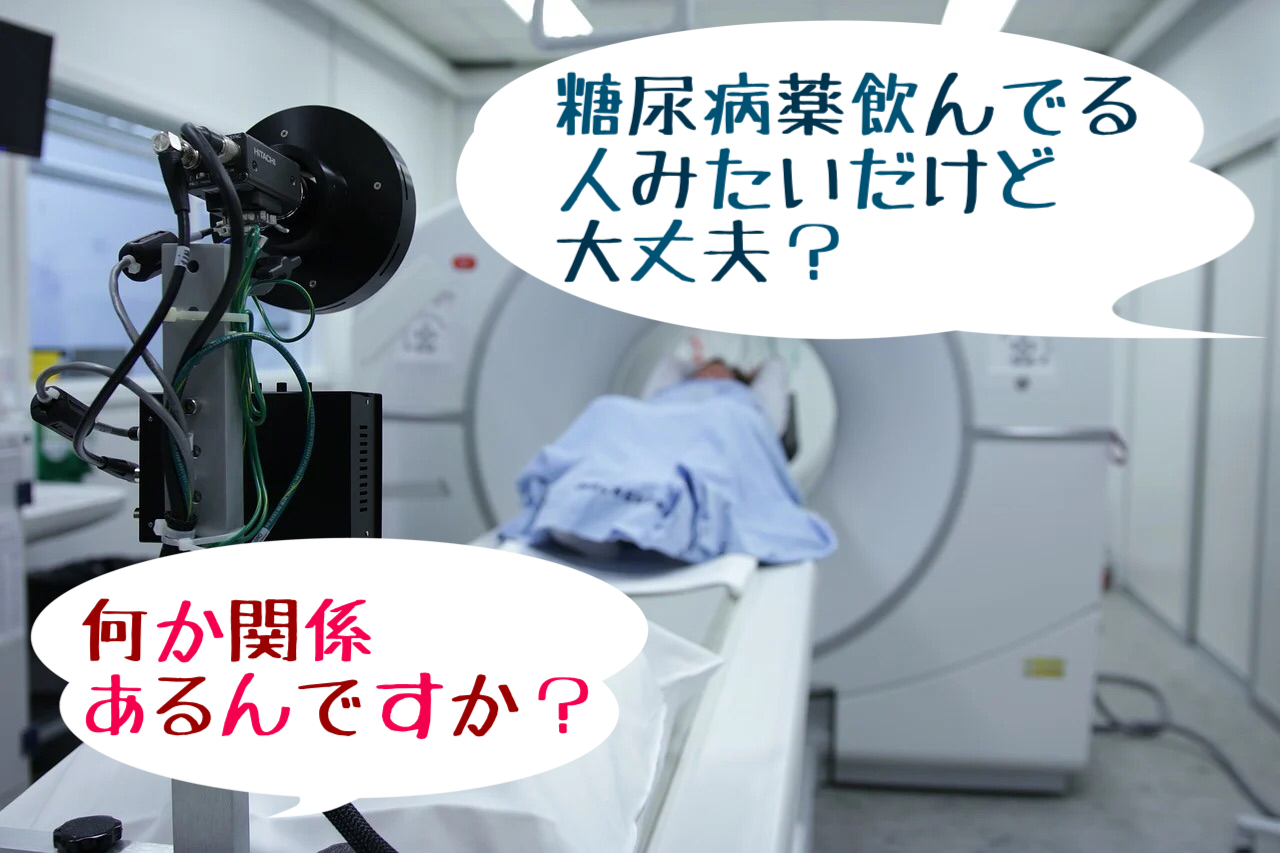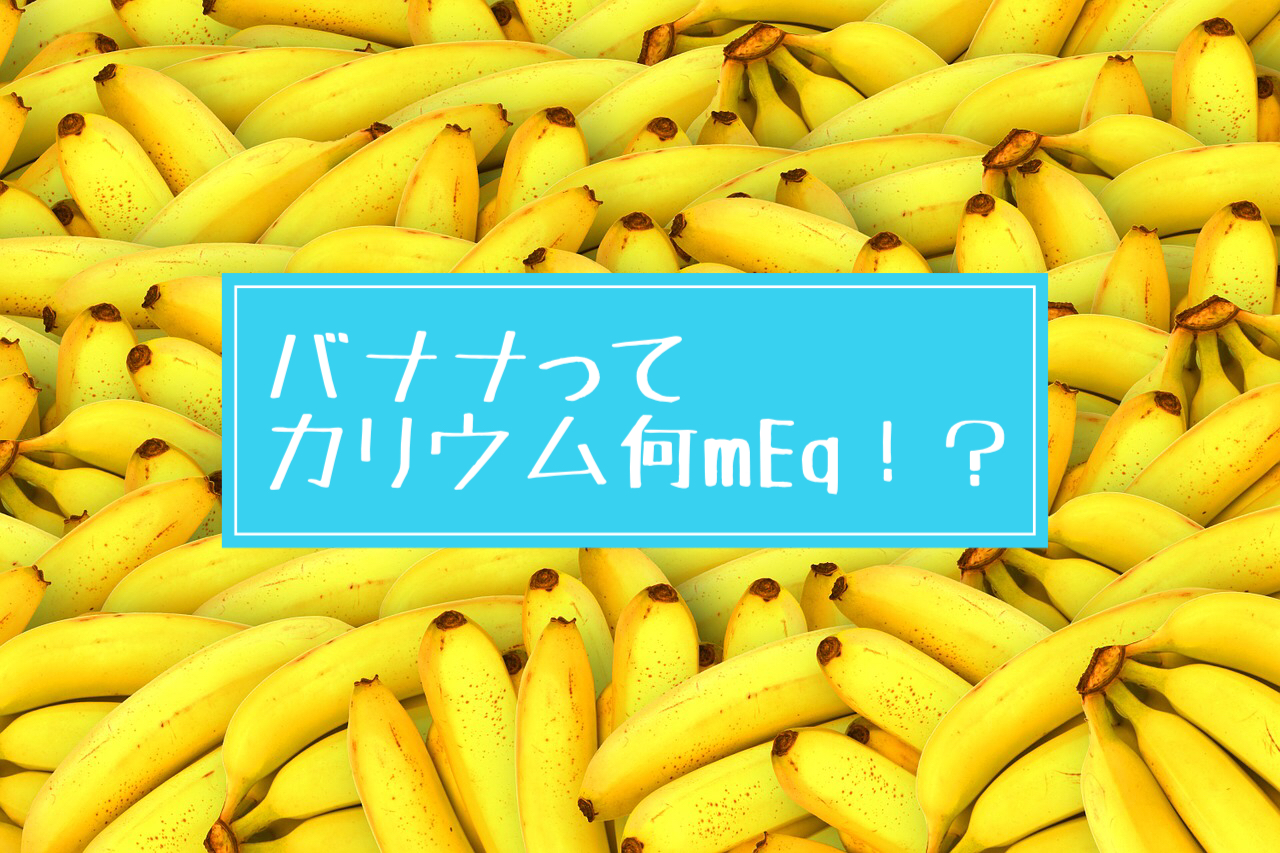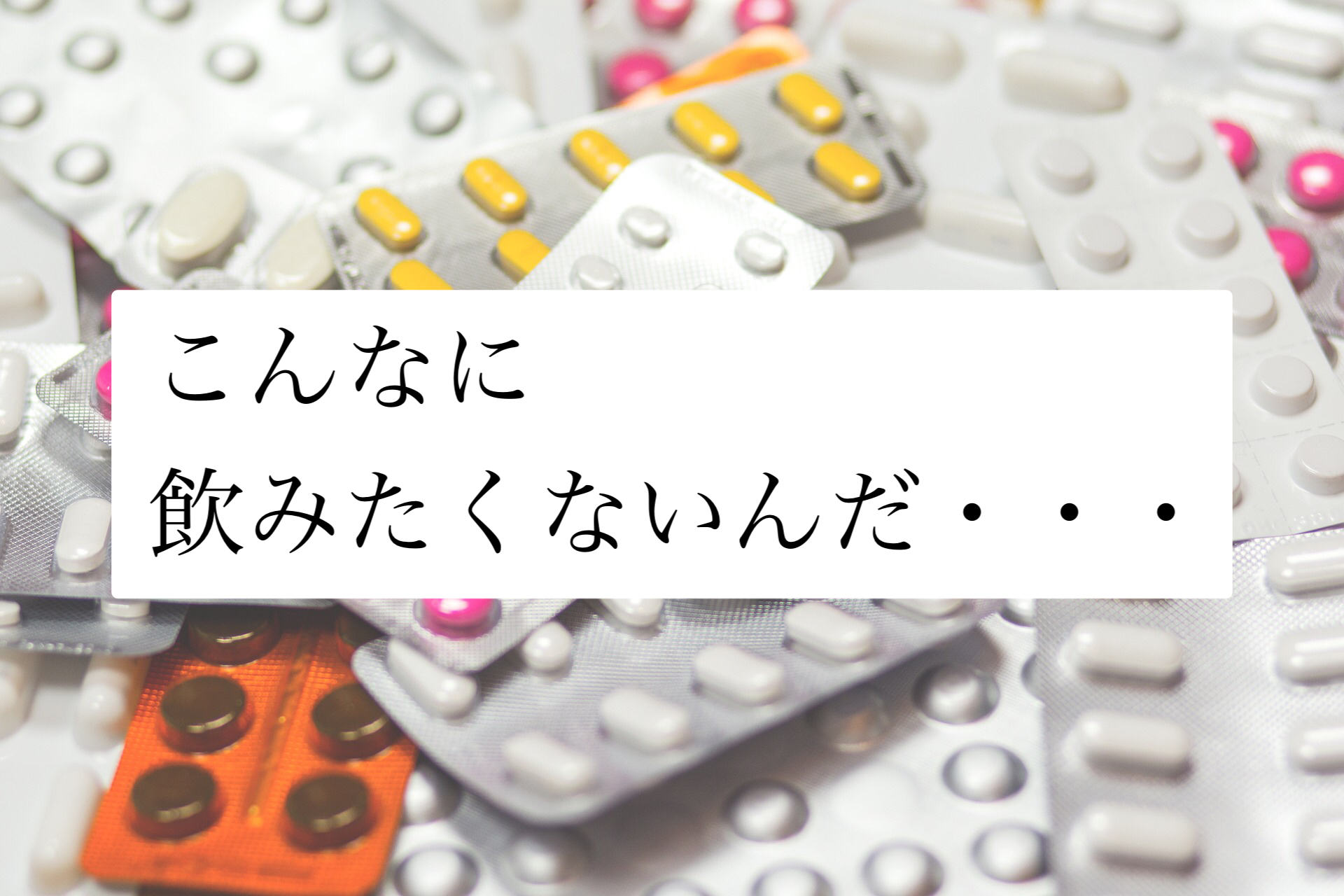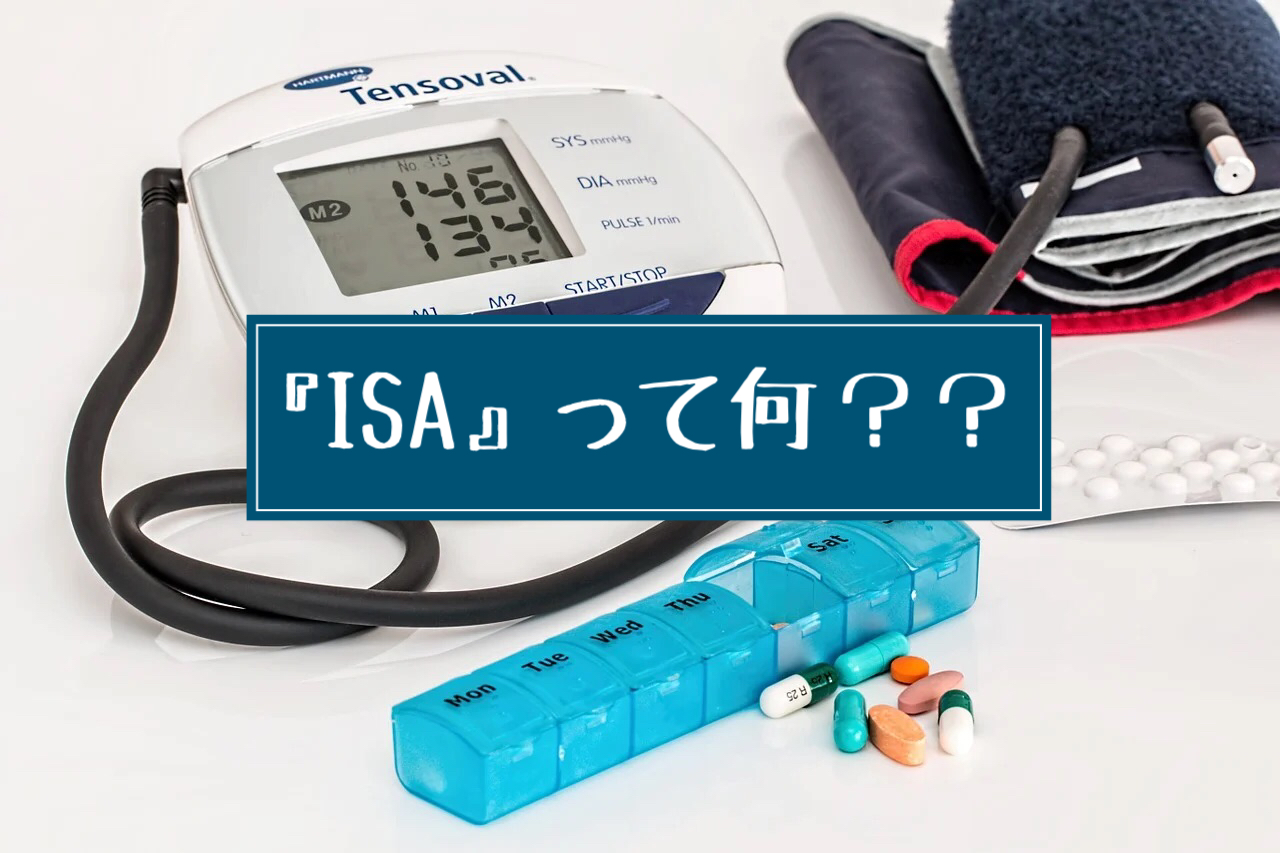こんにちは!今回は薬膳における【五味】について説明します!
これを知り、いつも食べている食材がどこに当てはまるのか意識して食べて、日々の食事で健康を維持していきましょう!
五味
【五味】とは、その名の通り5種類の味です。
- 辛味(シンミ)
- 甘味(カンミ)
- 酸味(サンミ)
- 苦味(クミ)
- 鹹味(カンミ)(塩辛い)
この5種類は、味だけでなくその働きに対しても分けられているので、例えば実際は辛くないのに『辛味』に分別されている食材もあります。
また、それぞれの味は体の特定の臓器と結びついています。何を食べるとどの臓器に働きかけるのか、どんな作用があるのか知ると、食材の選択もしやすいと思います。
それぞれどのような働きを持つのか見ていきましょう。
辛味
『辛い味は発汗作用がある』とよく言われますよね。辛味には体を温めて血行をよくする作用があります。
肺・大腸の臓器を補う作用があるため、肺の機能を改善させて痰を減らしたり、大腸を温めて胃腸の調子をよくしたりしてくれます。
食べすぎると腎臓機能が悪くなり、むくみやすくなったりします。また、体がほてりやすい人は食べすぎない方がいいです。
主な食材
ネギ、シナモン、トウガラシ、ショウガ、チンピ など…
甘味
よく「甘いの食べてストレス発散!」と言って、食べすぎちゃう人っていますよね。最近ではデザートの食べ放題のお店もたくさんあります。このように、甘味には疲れを取ったり、滋養強壮作用の働きがあります。
甘味に分類される食材は多く、食材の半分以上は甘味に分類されます。
脾・胃の臓器を補う働きがあります。脾や胃が弱ると食欲不振、消化不良、胃もたれなどを起こしやすくなるため、そのような状態になりやすい方は積極的に食べましょう。
食べすぎると糖尿病の危険性がありますし、胃もたれを起こしやすくなります。
主な食材
ハチミツ、トウガン、ダイズ、ジャガイモ、鶏卵 など…
酸味
「酸っぱい」味の酸味には、体の水分が出ていくのを止める働きがあります。下痢、汗、咳、おりものなどを止めてくれます。
肝・胆の臓器を補う働きがあります。ビール以外のお酒は主に辛味に属しますが、飲みすぎると肝臓にダメージを与えます。おつまみに酢の物が多いのは、お酒による肝へのダメージを和らげる力があるからです。
酸味を取りすぎると、体の水分を出さなくなり。消化吸収機能が低下します。
主な食材
梅干し、レモン、リンゴ、トマト、ブドウ、黒酢 など…
苦味
苦味には上半身にたまった熱を取り、尿を出しやすくする働きがあります。ほてりやのぼせ、高熱が出たときに摂取するのがおすすめです。
苦味には心の臓器を補う働きがあります。心が傷つくと血液循環が乱れ、息切れ、動悸などが起こりやすくなると言われています。また、精神的に不安定になり、不安感や不眠を引き起こします。苦味にはこれらを防いでくれる力があります。
苦味を摂取しすぎてしまうと、体の熱を取りすぎてしまい、胃腸が冷えやすくなります。
主な食材
ゴーヤー、ゴボウ、緑茶、タケノコ など…
鹹味
鹹味とは塩辛い味のことを指します。塩ってナトリウムが含まれてますよね?これが大切なミネラル源になります。また、鹹味には体のしこりをやわらげる力があるとされています。
腎・膀胱の臓器を補う働きがあります。腎には臓器を温める力や水分代謝を調節する力があります。近年減塩ブームですが、あまりにも塩を取らなすぎると尿が出なくなったり、むくんだりします。
鹹味を摂取しすぎてしまうと塩分過多となり、高血圧となり、心臓に負担をかけすぎてしまいます。
主な食材
塩、醤油、アサリ、カニ、牡蠣、ひじき、昆布 など…
いかがでしたでしょうか。今回は薬膳で使われる用語【五味】について詳しく書いていきました。『薬膳』って聞くと「難しそう」「中華料理だけなのかな?」と思う方も多いはず。でも実際は、冬に体を温める目的で料理に“ショウガ”を加えるのも薬膳の考え方。和食でも十分活かせますし、「実はこれも薬膳だったんだ!」ということも多いです。小難しいことを羅列してしまいましたが、皆さんが食べている手料理も実は薬膳の考えと重なるんですよ。
参考文献:『マンガでわかる はじめての和食薬膳』武 鈴子 著
 | 価格:1,430円 |